地球は熱い
みなさんこんにちは
特殊水処理機『新ん泉』の櫻井です。

夏本番となり、今年も各地で猛暑の便りが聞かれると思われます。
ところがその猛暑でさえも涼しく感じられるのが、地表から深く入った地中の世界です。
地球は巨大な熱エネルギー物体であり、地中には熱水をはじめとして、様々な資源が存在します。
今回は熱水など地熱に関して考えてみましょう。
地熱と熱水噴出

東京渋谷で発生した天然ガス爆発事故によって都内で温泉が多数開発されていることが知られるようになりました。
火山がないのになぜ温泉があるのか?
それは地球そのものが「発熱体」だからです。
非火山地域であっても地下深部からの熱が伝わってきています。
この熱による地温の上昇率は100mにつき平均約3℃であり、地表の温度が20℃だとすると、単純計算では地下1000mでは50℃、地下3000mでは100℃を超えることになります。
その深度に溜まっている熱水を取り出せば、これもまた立派な熱資源です。
これらの熱水の多くは地表からの浸透水や大昔の海が地下に閉じ込められたり、地下のマグマから分離した水でできたものです。
これらの熱水は熱資源としてだけではなく、金銀はじめ貴重な金属資源を含む場合も多く、鉱物資源の開発に重要視されるようになってきました。
地球の表面は、何枚ものプレート(岩石層)で覆われていて、そのプレートの境界で熱水が噴き出ている「熱水噴出孔」が数多く見られます。
こうした噴出孔の周りにはバクテリアをはじめとして巻貝・エビ・カニ・チューブワーム・魚類など太陽エネルギーに依存する地表とは異なり、熱水噴出孔をエネルギーの供給源として存続し独自の生態系が形成されており、生物学的にも注目されるようになっています。
超臨界水
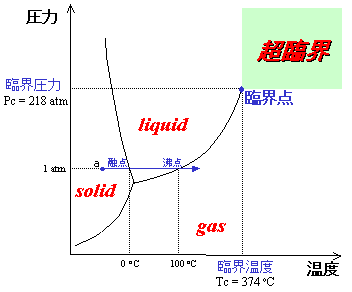
水は加熱すると1気圧100℃で水蒸気になります。
ところが圧力を高めると加熱しても気体にならず、温度を375℃、圧力を22MPaまで上げると、水でもない蒸気でもない均一な流体となります。
この点が臨界点で臨界点以上の状態を超臨界水と呼び、この水による反応を超臨界水反応と呼びます。
熱水噴出孔から噴出する水は水温は400°Cにも達し、超臨海水の状態のものが多く見られます。
(周りの深海の水温は2°Cくらい)これらの超臨界水や臨界点よりもやや温度・圧力の低い熱水(亜臨界水)による反応を水熱反応と呼びますが、これらの「特殊」な水はどこにでも忍び込む気体の性質(拡散性)と、成分を溶かし出す液体の性質(溶解性)を持ち、かつその密度を連続して大幅に変化できる特長を持っています。
したがってこうした水熱反応を利用すれば、有機物の分子、例えばでんぷんやたんぱく質は、それぞれブドウ糖やアミノ酸に分解され、低分子化されることにより、固形分が液状化されます。
また、環境汚染物質のダイオキシンを安全に分解し、無害化できます。
しかも水熱反応は、有機溶媒のような化学物質でなく、水を溶剤として使用するため、環境に優しい安全な反応と言えます。
食品、医薬品分野、公害防止分野での応用が期待されています。
環境にやさしい地熱発電

地熱発電は地下のマグマだまりの熱エネルギーによって生成された天然の水蒸気をボーリングによって取り出し(最初から蒸気の場合と、高温・高圧の熱水を減圧沸騰させて蒸気を得る場合がある)、その蒸気により発電機を駆動して電気を得る発電方式です。
再生可能エネルギーの一種であり、石油などの枯渇性エネルギーの価格高騰や地球温暖化の対策手法としても利用拡大が図られつつあります。
日本は火山が多く地熱開発の技術水準も高いのですが、地熱発電の総容量はおよそ561MWで世界第5位であるにもかかわらず、国内発電能力の1%にも満たない状態です。
日本で地熱発電が積極的に推進されにくい理由は、地域住民の反対や法律上の規制があるためです。
つまり、候補地となりうる場所の多くが 国立公園、温泉観光地となっていて、景観の点や温泉への影響懸念、国立公園での規制があります。
例えば、群馬県の嬬恋村では、その予定地が草津温泉の源泉から数kmしか離れていないため、温泉に影響が出る可能性があるとして反対が起きています。
地熱発電は石油などの化石燃料を使わないクリーンエネルギーであり、石油に匹敵する貴重なエネルギーを国産で採掘できることから、原油価格の変動リスクがない国産エネルギーとして、見直しが必要です。
費用対効果も向上しており、近年の実績で8.3円/kWhの発電コスト(水力11.9円、石油10.7円、原子力5.3円)が報告されています。
既存の温泉などとも競合しにくい高温岩体発電を利用すれば38GW以上(大型発電所40基弱に相当)におよぶ資源量が国内で利用可能と見られて国内電力の最大3割程度を賄える可能性があります。
太陽光発電や風力発電に加えて地熱発電の開発も進めるべきだとの指摘がなされています。
自然エネルギーの中でも、出力が不随意に変動する太陽光発電や風力発電とは異なり、需要に応じて安定した発電量を得られる地熱発電は地球全体でみた資源量も大きく、特に日本のような火山国においては大きなポテンシャルがあり、今後の推進が必要と思われます。


